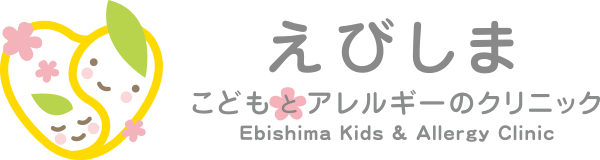秋から冬へと移りゆくこの季節、朝晩の冷え込みがぐっと強まり、空気も少しずつ乾燥してきました。お子さんの咳や鼻水、皮膚の乾燥が増える時期でもあり、体調管理に気をつけたい季節です。インフルエンザやRSウイルス感染法など冬に流行する感染症の患者さんも増えてきています。また突然気温が下がるとぜん息の発作も増えます。風邪かなあと思ってもぜん息の発作の咳のこともありますので、気になる症状があればご受診ください。

ガウンテクニックを全員で実習

外部講師をお招きして医療安全と接遇研修
当院では先日の休診日に、スタッフ全員で 院内の感染症対策・医療安全・接遇に関する研修 を実施しました。日々の診療のなかで「当たり前にできているつもり」のことも、定期的に振り返ることで改善点が見えてきます。院内の動線や消毒手順の確認、スタッフ同士の声かけ、患者さんへの説明の仕方など、医療の質と安全を守るために欠かせない時間です。より安心して受診していただける体制づくりを今後も進めていきたいと思います。
さて今日はビタミンDのお話です。先日の小児アレルギー学会でもビタミンDの教育講演がありました。
ビタミンDは 骨の成長や免疫機能に関わる栄養素 です。
不足すると、乳幼児では骨の発達が障害されて「くる病」が起こることがあります。くる病は昔の病気と思われがちですが、実は近年、再び増えてきています。
その背景には、
- 母乳栄養のお子さんの増加(母乳は栄養豊富ですが、ビタミンD含有量は少ない)
- 日焼け対策による屋外活動時間の減少
- 食生活の変化で、ビタミンDを含む魚類や卵の摂取量が減っている
などが関係しています。
ビタミンDは母親から子どもに胎盤を通じて移行するので、ビタミンDが不足しているお母さんから生まれたお子さんは先天的にビタミンDが不足しています。
軽度の欠乏では症状が目立たないため、「気づかないまま成長」が起こりやすく、血液検査で初めて分かることも珍しくありません。近年は、免疫機能やアレルギー、感染症との関連も研究されており、「骨だけの栄養素」ではないことが分かってきました。
◆ ビタミンDをどう補えばよい?
ビタミンDは 3つの方法 で補うことができます。
✅ ① 日光にあたる(皮膚でビタミンDが作られる)
- 午前中の外遊びや散歩で 10〜15分程度 顔や腕に日光が当たればOK
- 真夏の直射日光のような強さは不要
- 日焼け止めをしっかり塗っていると合成量は減少しますが、完全にゼロになるわけではありません
✅ ② 食べ物から摂る
|
食材 |
ビタミンD量が多いもの |
|
魚類 |
鮭、サンマ、イワシ、サバなど |
|
卵 |
特に卵黄 |
|
きのこ類 |
椎茸、きくらげ(天日干しだとさらに増加) |
✅ ③ サプリメント(特に乳児では推奨されることがある)
- 海外では「乳児はビタミンDサプリを毎日摂取」というのが標準となっている国もあります
- お子さん用のビタミンDシロップを母乳栄養のお子さんにお勧めしています
ビタミンDの1日あたりの目安量(年齢別)
年齢別の目安量を下にご紹介しますので、お子さまの世代に合わせて“だいたいこのくらい”という目安にしていただければと思います。
- 生後0~5か月:1日あたりおよそ 5 µg(マイクログラム) が目安です。
- 生後6~11か月:同じく 5 µg/日 を目安としています。
- 1~2歳児:およそ 3~4 µg/日 の摂取を目指しましょう。
- 3~5歳児:おおよそ 3.5~4 µg/日 が目安です。
- 6~7歳児: 4.5~5 µg/日 程度、8~9歳児では 5~6 µg/日 程度が目安となります。
- 10~11歳児であれば、 6.5~8 µg/日 程度が望ましい量です。
- 12~14歳ではおよそ 8~9.5 µg/日、そして 18歳以上の男女では9.0 µg/日程度(通常の食事をしている場合) が一般的な目安となっています。
これらの数値は「通常の生活・日照・食事環境」を前提とした目安です。冬場など日照時間が短くなったり、屋外活動が少ないお子さま、魚や卵・きのこ類の摂取が少なめなご家庭では、これらの目安量を 少し上回る意識 を持つことが大切です。
また、これらが最低限の目安であり、「この量を摂れば十分」というわけではありません。食事・日光・必要に応じた補助(サプリメントなど)を組み合わせて、バランスよく摂取することが望ましいです。
例えば鮭の切り身1切れ(約80 g)には、約25.6 µgのビタミン Dが含まれており、成人の日々の目安量を十分にクリアできます。魚類を毎回とは言えなくても、週数回取り入れられればお子さまの栄養補給にも大きな助けになります。卵黄・きのこ類も“少量でも毎日プラス”がポイントです。
子どもの栄養や健康管理は「気をつけたいけれど、毎日完璧にはできない」というのが本音かと思います。大切なのは“できる範囲で続けること”。完全を目指すより、少しずつ積み重ねるほうがずっと効果的です。当院は、子育て中のご家族にとって“相談しやすい場所”でありたいと願っています。ご家族からの相談でこちらも勉強になることがたくさんあります。気になることがございましたら、いつでも、お気軽にご相談ください。