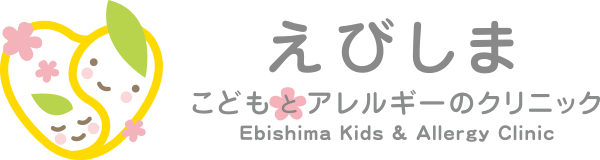朝晩の空気がひんやりして、すっかり秋らしくなってきましたね。
今月は運動会がある学校も多く、子どもたちは練習にがんばっていることと思います。疲れが出やすい時期でもありますので、体調の変化には気をつけてお過ごしください。
私たち医療スタッフにとって、秋は「学会シーズン」です。10月は「日本小児アレルギー学会」と「日本アレルギー学会」という、2つの大きな学術集会が開催されます。
先日4日・5日に大阪で行われた日本小児アレルギー学会に、看護師と一緒に参加してきました。私は残念ながら拝聴できませんでしたが、ノーベル医学生理学賞を昨日受賞されました坂口志文先生の特別講演もありました。珍しい症例の報告や今後の診療に役立つ内容、栄養指導など学ぶことはたくさんありました。また今回は「若手企画」というセッションで、AI(人工知能)について学ぶ機会がありました。ChatGPTをはじめ、さまざまなAIツールの活用法を紹介していただき、とても勉強になりました。学んだことを今後の診療や情報発信にも活かしていけたらと思っています。
今日は、「アレルギー性鼻炎をきちんと治療すると、食物アレルギーも改善することがあります」というお話です。
数か月前、食物アレルギーの兄弟が受診されました。お兄さんは乳児期から乳アレルギーがあり、200㎖の牛乳は飲めるようになったものの、牛乳を飲んで運動するとアナフィラキシーを起こしてしまう状況でした。弟さんは大豆アレルギーで、食物経口負荷試験や自宅で豆類を摂取すると、数時間後にアナフィラキシー症状が出るため続けられず悩んでおられました。診察時に『鼻』を診ると、どちらもアレルギー性鼻炎の所見があり、血液検査ではダニにも反応がありました。ダニのアレルギー性鼻炎に舌下免疫療法を行うことで、食物アレルギーの改善が期待できるという症例報告がありましたので、そのことをお伝えし、鼻炎の治療としてダニの舌下免疫療法(舌下免疫療法については病気から調べるhttps://ebishima-kids.com/menu/medical06/を参照ください)を行うことをおすすめしました。食物アレルギーについて、兄は摂取後の運動誘発を伴う食物負荷試験、弟は遅発型反応のため入院での負荷試験が必要と判断し、神戸の専門施設に紹介しましたところ、食物経口負荷試験の前に、同施設でダニおよびスギに対する皮下免疫療法を先行開始する方針となりました。皮下免疫療法により鼻炎症状は著明に改善し、春季のスギ花粉の時期も症状なく過ごされたようです。さらに夏に実施された食物経口負荷試験では、兄は牛乳200ml+プロテイン摂取後に運動負荷を行っても症状を認めず、乳の制限が解除。弟も豆腐50g摂取で症状がなかったということでした。また入院中は、管理栄養士から栄養指導も受けることができ有意義な時間だったようです。兄弟ともに食事制限が緩和され、「世界が変わった」と保護者の方が喜ばれたことが印象的でした。お兄さんの国内留学にも間に合い、保護者の方も安心して送り出すことができそうで何よりです。
今回の経験から、アレルギー性鼻炎が食物アレルギー反応のトリガーの一つとなり得ること、またアレルギー疾患は全体として診る重要性を改めて認識しました。アレルギー性鼻炎は気管支喘息の悪化の原因になりますし、アレルギー性鼻炎をきちんと治療すれば気管支喘息の発症を予防することもできることを考えると、アレルギー性鼻炎って様々なアレルギー疾患のトリガーになっているのだなあとつくづく感じました。
『診察で鼻を必ず診ること』と教えられ、最初は小児科医が鼻を診るの?と思い、所見の取り方もわかりませんでしたが、何十年もやっていると、アレルギー性鼻炎と風邪の鼻の所見の違いも徐々に分かってきました。日本アレルギー学会の言うTotal allergistを目指して、今後も「鼻を診る」を続けていこうと思いました。